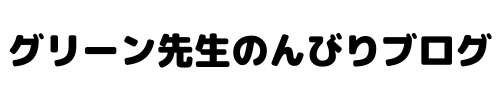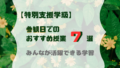子育てをしていると、様々な不安を感じることがあると思います。
- 友達とのトラブルが多い気がするが、友達とうまく関わることができているのか?
- 自分の子どもが授業についていけているのか?
- このままの環境で過ごしていてよいのか?
複数のお子さんがいらっしゃる保護者の方は、きょうだいと比べて不安になることがあるでしょうし、はじめての子どもで比較対象がいないから、基準が分からないと感じられる方もいるでしょう。

今回は、こんな悩みを少しでも解決できればと思います。
わたしの経歴はこちら
- 小学校教員 14年目
- 通常学級担任 1、2、4、5、6年担任を経験
- 現在特別支援学級(知的障害)担任 1、2、3、4年担任を経験
- 生徒指導主事3年目
特別支援学級がよいのか?通常学級がよいのか?
これまで保護者の方から相談を受けたものには・・・
- 学習をよく理解できていないのではないか不安
- このまま通常学級でよいのか? など
真剣にお子さんのことを考えられているがゆえに、感じる悩みだろうと思います。
実際、私自身も通常学級の担任をしながら、目の前の子どもにとってよりよい環境は?どのように支援することが適切なのだろう?と日々悩んでいました。
そこで、今回はつぎの4つのことについてまとめたいと思います。

- 特別支援学級とは?特別支援学級の基準は?
- 特別支援学級のメリット
- 特別支援学級のデメリット
- 一度、特別支援学級に入ると、通常学級へ戻れないのか?
特別支援学級とは?
小学校、中学校等において以下に示す障害のある児童生徒に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために設置される学級。
【対象障害種】
2.特別支援教育の現状:文部科学省 (mext.go.jp)
知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び身体虚弱者、弱視者、難聴者、言語障害者、自閉症者・情緒障害者
特別支援学級の学級編制の標準は現在8人とされているが、複数の学年の児童生徒を同一学級に編制することが認められている上、在籍する児童生徒の障害の重度・重複化等の学級の実態を踏まえ、学級編制の標準の引下げの要望が多い。
関係資料2:今後の学級編成及び教職員定数の改善について(提言)【概要】:文部科学省 (mext.go.jp)
特別支援学級の基準や入級の流れ
特別支援学級に入る基準というものは、実際、明確に定められているわけではありません。各自治体によってもさまざまだと思います。
保護者の方が希望されるから必ず入級できるというわけではなく、専門家による検査や審議が必要です。
知的能力障害(ID: Intellectual Disability)は、医学領域の精神遅滞(MR: Mental Retardation)と同じものを指し、論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、学校や経験での学習のように全般的な精神機能の支障によって特徴づけられる発達障害の一つです。
知的機能は知能検査によって測られ、平均が100、標準偏差15の検査では知能指数(Intelligence Quotient, IQ)70未満を低下と判断します。しかしながら、知能指数の値だけで知的障害の有無を判断することは避けて、適応機能を総合的に評価し、判断するべきです。
知的障害(精神遅滞) | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
私が通常学級の担任をしていた児童は、このような流れで知的障害特別支援学級へ入級しました。
- 保護者の方から発達支援センターへ電話で相談依頼
- 発達支援センターにて子どもの様子を相談
- 学校での様子を発達支援センターの専門家による訪問相談(相談員、言語聴覚士、作業療法士など)
- 児童の特性を理解するための発達検査など
- 訪問相談や発達検査の結果を報告、支援方法について相談 → 個別の指導計画の作成
- 市教育委員会等の専門家による審議
学校への初めの相談は1年生の終わりで、実際に2年生になって動き始め、2年生の2学期から入級という感じでした。
いずれにせよ、外部の専門家による検査や審議などがていねいに行われ、特別支援学級が適当であると判断された場合に入級することになります。
特別支援学級のメリット
ここからは、特別支援学級のメリットについて紹介します。

- 少人数学級による指導(最大8人)
- 下の学年の学習を復習したり、繰り返し練習したりできる
- 特別支援学級担任や支援員による個別の対応
- 子どもの得意分野を伸ばすことができる
- 子どもの特性に合わせた学習ができる(通常学級にはない教科・・・自立活動)
- 異学年の児童との交流が自然とできる
- 通常学級の児童との学習が適した教科は、交流学級(通常学級)で授業を行うことも可能
特別支援学級のデメリット
- 通常学級の児童と関わる時間が減る
- 大人数での活動に抵抗感が出る場合がある(少人数の居心地の良さを感じてしまう)
- 集団の中での児童の様子が把握しづらい(他の児童との比較がしづらい)
- 周囲の人から偏見や心無い言動に傷つく可能性がある

一度、特別支援学級に入ると、通常学級へ戻れないのか?
特別支援学級に入級する児童は、審議の結果、この環境が適当であると判断された結果、入級しているのですが、児童によっては、適切な支援や本人の成長により学年が上がるにつれて「通常学級で学習することが適切?」という場合ももちろん出てきます。
正直、稀なケースではありますが、特に、低学年の頃から特別支援学級で学習している児童の中には、高学年や中学生になって通常学級で学習することにした子どももいました。
ですので、子どもにとって適切な学習環境を学校と家庭が連携を取りながら、その都度考えていくことが必要だと思います。
一人で悩んで苦しまず、ぜひ学校や発達支援センターへ気軽に相談してもらえれば幸いです。