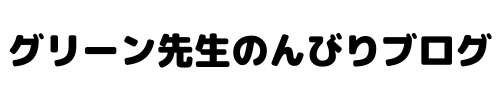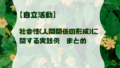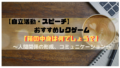児童の中には、様々な理由で家庭学習の習慣がなかなか身に付かない児童がいます。
どうしたら、宿題をやってこれるようになるんだろう・・・と私も幾度となく悩みました。

今回は、そんな悩みを解決する手掛かりになればと思います。
わたしの経歴はこちら
- 小学校教員 15年目
- 通常学級担任 1、2、4、5、6年担任を経験
- 現在特別支援学級(知的障害)担任 1、2、3、4、5年担任を経験
- 生徒指導主事4年目
この記事を読めば、分かること!
- どうして宿題をやってこない?
- 家庭学習を身に付けるための方法4選 ~家庭編~
- 家庭学習を身に付けるための方法5選 ~学校編~
あわせて読みたい記事
どうして宿題をやってこない?
宿題は、毎日するものなのに、どうして家でやってこないのでしょう?
今回は、まずその理由を考えてみます。主に5つの理由があるのではないかと思います。
- 家庭環境 ・・・ 児童の家庭での学習環境が整っていないことで、学習に取り組むことが難しい場合があります。テレビやゲームが近くにある、大きな音(周囲の騒音、きょうだいの声)が聞こえる、部屋が散らかっているなど。このような環境では、なかなか集中して学習に取り組むことはできません。また、学習面での保護者のサポートが不十分である場合も考えられます。
- 経済的な問題 ・・・ 貧困層の家庭では、経済的な問題が学習に影響を与えることがあります。筆記用具、ノート、辞書などの学習に必要な道具がそろわないことで、学習の機会に制約を受けるということです。
- 児童の特性 ・・・ 児童が学習障害や学習に困難を抱えている場合、学習が難しいことがあります。このような場合、個別の教育支援が必要となることがあります。
- モチベーションの低下 児童が学習に対するモチベーションを持っていない場合、自主的な学習が難しいことがあります。学習する意味を伝えたり、学習する意義を体感できるようにサポートすることでモチベーションを高めることができます。
- 社会的要因 いじめや学校への不適応により、学習への集中力が低下することがあります。まずは、これらの問題の解決が必要です。
上に示した理由を考えると、児童の怠惰だけが原因ではないかもしれません。
やってこようと思っているけど、やってこれない・・・という場合もあるということも知っておく必要があります。
また、理由1、2にも関係をしてくる問題ですが、現在は、ヤングケアラーが社会的な問題として取り上げられることが増えました。
ヤングケアラーとは
・ 障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている
・ 家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている
・ 障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている
・ 目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている
・ 日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている
・ 家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている
・ アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している
・ がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている
・ 障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている
・ 障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている
こどもがこどもでいられる街に。~ヤングケアラーを支える社会を目指して~ 【厚生労働省】 (mhlw.go.jp)
このような家庭環境にある児童に関しては、家庭での学習習慣以前です。早急に福祉との連携が必要ですので、各自治体と情報共有をして、児童の健全育成に努めましょう。
家庭学習を身に付けるための方法4選 ~家庭編~
では、児童が宿題をやってこれない理由を理解した上で、どのような手立てができるでしょうか。
家庭との連携ができる場合は、まずはそこを試してみましょう。
学級担任が悩んでいるのであれば、保護者の方も悩んでいることでしょう・・・

しかし、ただただ「お子さんは、毎日宿題をやってこなくて困っています」と伝えるのでは解決になりません。不信感を与えるだけです。
どうやったら家庭での学習習慣が身に付くかをいっしょに考え、いっしょに実践していくことが必要です。

では、家庭でできるおすすめの方法を4つ紹介します。
1 学習環境の整える
保護者との連携を図り、児童が落ち着いて学習に取り組める環境作りをします。
静かな環境の方が取り組みやすい場合は、個室で学習に取り組むのをおすすめします。
中には、保護者の目の届くところがよいという場合もあったり、部屋数などの物理的な面もあったりすると思うので、個室が難しい場合は、パーテーションで区切る、ヘッドホンを付けるなどの工夫もできます。

2 学習時間を確保する
「帰宅後すぐに学習に取り組む」「4時になったら取り掛かる」など、学習する時間を設定しておくとよいです。毎日、同じ時間に活動することで、生活リズムが定着します。
3 時間を区切る
集中力が続きにくい場合は、タイマーを活用し「ここまでを15分でしよう」「5分休憩したら30分取り組もう」など、時間を区切って行うのも有効です。

4 できたら褒める
決められた場所で決められた時間、決められたことができたら、しっかり褒めます。
当たり前のことだと思わず、褒めることで児童に「こうすれば褒めてもらえる」「できてうれしい」という成功体験をさせましょう。

家庭学習を身に付けるための方法5選 ~学校編~
次に、学校でできるおすすめの方法を5つ紹介します。
1 児童といっしょに目標を設定する
目指す姿を共有し、短期目標・長期目標をいっしょに考えましょう。
児童に「どんな自分になりたい?」と聞くと、「約束を守る」「忘れ物をしない」「宿題をちゃんとする」などの答えが返ってくるはずです。
そこで、「じゃあ、少しずつでも目標を決めてやってみよう」と提案し、児童と合意のもと、スモールステップで進めるのがよいでしょう。
- 漢字は必ずする
- 漢字と計算は必ずする
- 漢字と計算ともう1つ自分で選んで必ずする
- みんなと同じものを必ずする など

2 宿題を児童に合ったものに代える
児童が学習に困難を抱えている場合は、保護者の方と相談して、児童に合った宿題を出すというのも一つの手です。
難しくて、やる気が出ない。やってきても、直しばかりさせられる・・・という毎日では、学習意欲は低下します。継続して学習することも難しくなるかもしれません。
前向きに家庭学習に取り組むために、児童の能力に合ったものを選ぶということも大切です。

3 宿題の内容を児童自身に選ばせる
これは、驚く方法かもしれませんが、実は家庭学習を身に付けさせるための方法として有効なのかもしれないと最近、思っています。
実際、現在、担任している児童の一人は、宿題をしてくる習慣が全くありませんでした。
しかし、ある日を境に毎日のようにしてくるようになりました。出しているのは、いつも同じ「プリント1枚」という宿題です。
変わったことは「自分で宿題プリントを選ぶ」ということです。もちろん、内容は教師が確認し、最終的には決定していますが、案外、これなら自分でできそう!とよく考えて、毎日選んでいるように見えます。
宿題の意味は、現在賛否両論ですが、私は、学校での学びの確かな定着を目指して行っていると考えています。
自分が学びたいことを選んで学習するというのも新たな方法かもしれません。
4 帰りの会の時間に宿題の取り掛かりをする(5分程度)
この方法は、高学年を担任していた時に、少し取り入れていた方法です。
帰りの片付けが速くできた児童から、帰りの会が始まるまでの時間に宿題をしてもよいというルールにしておき、宿題の取り掛かりをするという方法です。このようにすることで、帰る準備も早くなります。
また、宿題の取り掛かりを少ししておくことで、帰って急に宿題をスタートするよりも取り掛かりのハードルが下がります。あの続き、やろうか・・・と取り掛かりやすくなります。

5 できたら褒める
これは、家庭でも学校でも同じです。子どもの成長はとにかく褒めることからだと思います。
- 今まで宿題をしなかった児童が1つでも宿題をやってきたら、褒める。
- 続けてやってきたら、めちゃくちゃ褒める。
- 宿題をやってきたら、ノートにシールを貼っていき、10個たまったら、宿題なし!
など、ときにはご褒美を与えながら、いっしょに楽しみながら学習を進められたら・・・と思っています。

少しでも悩みの解決につながればうれしいです。